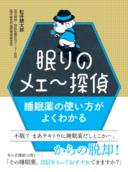高齢者の精神診療と処方 これだけは!
★2025年6月下旬 発売予定!★
臨床医が精神科のサポートなしで、高齢者へ向精神薬を処方する際に役立つ!
内容紹介
超高齢化社会において、一般臨床医が高齢者の精神診療にあたる機会が増えてきています。非専門医であるために治療に迷うことも多いでしょう。スムーズに精神科につなぐことができれば問題ありませんが、地方など環境が整っていない場合もあるのが現状です。治療の中心は、向精神薬による薬物療法が主体となります。そこで、すべての臨床医が精神科のサポートなしでも、高齢者のメンタルヘルスを診る時代に必要な基本知識と治療の考え方がわかるような内容としました。
序文
はじめに
2024年の「敬老の日」に日本における最新の高齢者数の推計が総務省統計局から公表されました。65歳以上の高齢者人口は総人口30%近くに達する3625万人です。現在国内の医療施設で医療行為を行う医師は約33万人、すべての高齢者が治療を必要とするわけではありませんが、8割以上の高齢者が月に1回以上の通院をしていることが医療統計で分かっていますから、臨床医が高齢者の健康維持に単純計算でも医師一人あたり約100人の高齢者を担当しなければならない状況にあるのです。
筆者が精神科医になった1990年代前半では高齢者のメンタル不調といえば、精神科が担当するものであり、精神病院には認知症(当時は痴呆症)を中心に慢性精神疾患を有する高齢者を治療するいわゆる「老人病棟」が存在しました。これが2000年の介護保険制度の制定により高齢者の在宅介護の開始や老人保健施設が開設されたことにより、高齢者医療を精神科のみで診る時代は終わり、すべての診療科医療機関が高齢者医療の健康維持に関するすべてを診る時代へとなったのですが、実際にはどうでしょうか?
認知症の治療であれば自信があるという医師でも、多彩な精神症状を呈するケースへの対応は十分と言えないので精神科に治療を依頼するということが多いのではないでしょうか? 冒頭にも述べましたように、今後は精神科医に治療を依頼することすら難しい医療環境に変化します。このような状況を踏まえると老年期ヘルスケア全般に関する詳しい知識が今後求められるようになるのは必至と考えます。
本書は、高齢者のメンタル不調に関する知識・理解・治療の解説と、高齢者のヘルスケア維持に医療がどのように貢献できるかも含めた内容を解説したものです。
これらの内容が基盤となって、各診療科目のアレンジが加わり、新しい老年期医療へと発展し、さらには社会福祉に貢献できる医療を提供できる一助となれば幸甚です。
2025年春
姫井昭男
目次
序文
Chapter1 高齢者
超高齢社会で求められる医療
高齢者医療
高齢者の心身の変化
高齢者の栄養状態
高齢者の健康格差
高齢者の健康状態と中高年期の生活習慣
高齢者の生活実態と生活環境の影響
知覚の機能の加齢変化
認知機能に影響を及ぼす知覚障害
高齢者の身体と精神の老化自覚の乖離
Chapter2 高齢者の精神不調起因とその助長要素
高齢者特有の日常ストレス
環境変化によるストレス
高齢者の感情の変化
老年期精神障害の特徴
高齢者の社会性の欠如
Chapter3 高齢者の薬物療法 基礎知識
高齢者への薬剤投与での留意点
高齢者の薬物代謝
高齢者の薬物動態
高齢者の多病と多薬という現状
精神不調時における高齢者の身体変化
高齢者へ向精神薬を投与するとき
老年期精神障害の薬物療法の基本
老年期精神障害の治療方針
Chapter4 アルツハイマー型認知症
認知症
認知症の臨床診断と病理診断
現状の認知症診断における検査
認知症検診におけるトラブル
脳器質変化による認知症発症
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症の臨床像
アルツハイマー型認知症の治療薬
認知症治療薬を処方するときに伝えるべきこと
認知症治療薬の中止
非薬物療法
Chapter5 レビー小体型認知症
レビー小体
レビー小体の分布と疾患バリエーション
鑑別診断
レビー小体型認知症診断のための検査
レビー小体型認知症の特徴的な症状
レビー小体型認知症の病状進行
薬物療法
非薬物療法
補足
Chapter6 認知症の行動・心理症状
高齢者の精神症状
BPSD発現の助長因子
BPSDの薬物療法
関連知識:認知症に生じる幻覚・妄想の捉え方
関連知識:攻撃的行動(暴力行為)の原因
BPSDと漢方薬
関連知識:高齢者の食生活と精神症状
関連知識:チアミン欠乏と精神症状
関連知識:亜鉛欠乏と精神症状
Chapter7 高齢者の「うつ」
「うつ」の成因
「うつ」の捉え方
「フレイル」と「うつ」
老年期の「うつ」
「うつ」履歴のある高齢者の治療
初めて「うつ」を呈した高齢者の治療
抗うつ薬の効果
認知症の可能性が否定できない「うつ」の薬物療法
高齢者の「うつ」に対する非薬物療法
Chapter8 血管性認知症・脳梗塞後遺症・頭部外傷後遺症
血管性認知症
血管性認知症の症状と予後
脳梗塞後遺症・頭部外傷後遺症
薬物療法による改善の試み
脳梗塞後の予防的薬物療法
高齢者のてんかん
てんかんと神経伝達物質
高齢者に使用する抗てんかん薬
Chapter9 睡眠障害とせん妄
高齢者の生体リズム
高齢者の睡眠障害
非薬物療法
せん妄
薬剤によるせん妄の惹起
せん妄の非薬物療法
せん妄の薬物療法
せん妄の薬物療法の中止方法
Chapter10 依存症
高齢者のアルコール依存症
依存症とは
依存症の正体はコントロール障害
依存症は「否認の病」
アルコール依存症に続発する症状
アルコール依存症治療薬
高齢者のニコチン依存症
ニコチン依存症の特徴
ニコチン依存症の治療
依存症専門医療機関との連携
啓発・安易にベンゾジアゼピン系薬剤を処方しないための知識:ベンゾジアゼピン系薬剤の薬理と依存形成
処方薬依存ハイリスク者の性質
依存症を発症すると発症前の性質と真逆になる?
依存症ハイリスク者
Chapter11 非薬物療法
適正な食事の啓発
脳科学的視点による高齢者の食事問題
高齢者のメンタルヘルス向上と必須アミノ酸
適正な運動(肥満解消)の啓発
老齢期の健康と若年での生活習慣改善啓発
Chapter12 高齢者支援への提言
メンタル障害の原因となる高齢者の抱えるストレス
高齢者の社会的孤立リスク:男性高齢者へのケアの重要性
生活習慣と男性高齢者の問題1
生活習慣と男性高齢者の問題2
介護関係者の意識改革の必要性
高齢者への“真の”サポート
Chapter13 留意したい高齢者の薬物療法
抗血小板剤
消炎鎮痛剤
過活動膀胱治療薬
降圧薬
プロトポンプ阻害薬(PPI)
視床下部作用性抗潰瘍剤
コラム
高齢者ドライバーの交通事故と認知機能
被害的思考と性差
「人格」と「性格」
高齢者の詐欺被害
ポリファーマシーの実際
「お薬手帳も見せて下さい」
高齢者とベンゾジアゼピン系薬剤
MCIの定義
神経細胞変性による認知症とバイオマーカー
高齢者のてんかん
認知症症状の悪化と脱水
タウタンパク質に関連する新しい知見
90年代の抗痴呆薬
病的体験の対応
カプグラ症候群(Capgras syndrome)
誤診されるレビー小体型認知症
注意障害と遂行機能障害
α-シヌクレイン
嗅覚と神経変性疾患
超高齢社会における「うつ」の精査と治療
なぜ「認知症」と思われてしまうのか
スルピリド
トラゾドン
退行(regression: 子ども返り)
ストレスとセロトニン
トリプトファンの摂取の重要性
フレイル
高次脳機能障害の特性と支援
頭部外傷後の幻覚・妄想を改善する薬物療法はない
グルタミン酸とGABA
ゾニサミドとパーキンソニズム
薬剤性せん妄
せん妄には“短期間の集中薬物療法”と“生活習慣改善による予防”
日本経済とアルコール依存症
脱水と飲酒
高齢者の食事の実像とオーラルケア
加工食品とメンタル不調
高齢者の診察を円滑に行う方法
コミュニティー機能の喪失
『時間の有効活用』=メンタル障害予防という啓発
“真の蓄え”の啓発
索引
プロフィール