深く息をするたびに
(原書名:Every Deep-drawn Breath : a Critical Care Doctor on Healing, Recovery, and Transforming Medicine in the ICU)
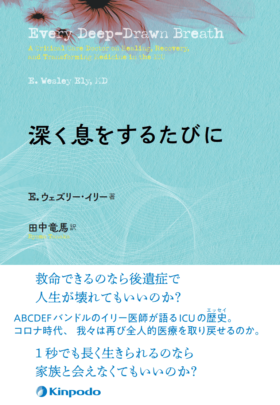
ABCDEFバンドルのイリー医師が語るICUの歴史。コロナ時代、我々は再び全人的医療を取り戻せるのか?
内容紹介
「集中治療室(ICU)」や「重症患者」が新型コロナの流行によりずっと身近になった現代、ICUサバイバー※の抱える問題に警鐘を鳴らし、対応策を提示するのが本書です。
集中治療のトップランナーであるE. ウェズリー・イリー医師がそれまでの集中治療室(鎮静や長期間にわたる安静)で問題となる集中治療後症候群(PICS)の発見、対策の検討の歴史や、救命絶対視からICUサバイバーの退院後の生活まで考慮した全人的な集中治療室を築くまでの歴史をエッセイで提示します。
ICUに携わる医療従事者、またICUサバイバーやその家族などすべての人に、より良いICUとはなにか?
全人的医療とは何か?を問いかけます。
※ICUから退院した患者さんを「ICUサバイバー」と呼びます。
原著付録の「患者、家族、医療者向けの情報」については下記URLよりご覧いただくことができます。
https://www.kinpodo-pub.co.jp/bk1937-9_1/
また、医療従事者の皆様で読書会をされる際に、ご活用いただける本書の読みどころについても下記URLにて公開しております。
https://www.kinpodo-pub.co.jp/bk1937-9_2/
序文
原著者まえがき
医学とは「善意」、すなわち善を願うものだと多くの人は信じているが、それ以上のものだ。医学が目指す規範は、もっと高い基準である「善行」、すなわち善を行うことでなければならない。これによって、患者と私の間に信頼が生まれ、それが私の技術と診療の基礎となる。信頼に応えるために、私は常に患者を助け、決して害を及ぼさないと約束する。病院に足を踏み入れるたびに、私はこの重大な約束を思い起こす。誓いといっていい。
医師になって最初の頃、私は道を踏み外した。意図的にではなかったが、医療でのあらゆる状況をコントロールしたいと願うあまり、私は十分に耳を傾けなかったのだ。私たちの最大の宝物は、深くて本物のコミュニケーションをお互いにとることにある。その宝物を育めば、特に病めるときには、二人の人間が神秘的ともいえる関係を築き、文化や社会、人種の壁を越えて、慈愛と共感の輪を広げることができる。このようなコミュニケーションがなければ、私たちの間は何キロメートルも隔たったままだ。
ICUの医師としてまだ若い頃、私は命を救うことに全力を傾けた。しかし、その過程で、患者の尊厳を犠牲にし、害を及ぼすこともあった。それは、アイコンタクトや会話というかけがえのない贈り物と引き換えに、「必要」と思い込み、薬剤によって昏睡状態にしたり、何百時間にもわたって深い鎮静をしたりしたときのことだ。患者やその家族が、次々と私の考えの誤りを明らかにしていった。私は誓いを破って、患者の医療における物語、つまり人生そのものにおける患者の声を奪っていたのだ。「まず、害をなすなかれ」という原点に立ち返るために、私はこの本を書くことにした。
良い知らせは、いまや私、いや私たちの理解が進んでいることだ。私は医師として、科学者として、同僚たちと協力して、単に治癒するだけ以上の方法を生み出してきた。本書で紹介したベッドサイドでのさまざまな体験を通して学んだことが、より大きなスケールで真実であると証明された。何千人もの患者が、彼らの時間、病気、血液を、国際研究のために使うことに同意してくれたのがそれを示している。これは、本当の意味で、彼らの物語なのだ。そして、彼らの人生は、医学の枠にとどまらず、私の人生のあらゆる瞬間に適用できる真実を与えてくれた。
ほとんどの人は、自身がICUに入室するか、命にかかわるような病気でICUに入室した家族を心配する立場になる。新型コロナのパンデミックでは、それがつらいほど明らかになった。コロナウイルス感染に対する私たちの厳重な隔離対策のために、何百万人もの人々が孤独に陥り、個性を失った。実際、私が望むことの一つは、この本で患者から不朽の教訓を学び、そこから治療者としてのアプローチを改善して、現在そして今後何十年にもわたって、将来のパンデミックの際に活用することだ。自らすすんで患者になることを選ぶ人はいないが、病衣を着た人の人間性を見失わずにいることは誰にでもできる。患者は、治療の対象としての心臓や肺だけではない。心も体も精神も、その人全体が危機に瀕しているのだ。
医療における私の「なぜ」は、まずふれあいを通じて患者の中の人間性を見出すことで、テクノロジーは二の次だ。人間性と思いやりといった強力な組み合わせを、現代のテクノロジーに組み込むことが、人に善を行う最良の方法だ。医師として前進し、さらにいえば、より良い父であり、息子であり、兄弟であり、友人であるための誓いなのだ。
E.ウェズリー・イリー,MD
訳者まえがき
本書を手に取ったみなさんにとって、「集中治療室(ICU)」や「重症患者」などは縁のない単語だったかもしれません。少なくとも、新型コロナ流行までは。
医療の歴史にICUが登場するのは比較的最近になってからです。1850年代のクリミア戦争の際に、イギリスの看護婦ナイチンゲールが、重症患者をより注意深く観察できるようにとナースステーション近くに配置したのがICUの始まりとされています(チャプター2)。そして、現在のような人工呼吸器が導入されるようになったのは、1952年のデンマークでのポリオ流行以降のことです。その後ICUは、人工呼吸器をはじめとする最新の技術・機器を活用することで、それまでは助からなかったような重症の患者さんを救命する場として発展を遂げ、2020年からの新型コロナ大流行で脚光を浴びるようになります。私自身も、医師として四半世紀ほどICUで働く中で、その歴史の一部を経験してきました。
ICUにはさまざまな原因による重症の患者さんが入院して、種々の薬剤や器械を使った治療を受けます。生死が危ぶまれるほどの重症であっても、無事に回復を遂げ、退院して自宅に戻られる方が増えているのは喜ばしいことです。がんから回復された方を「がんサバイバー」と呼ぶことがありますが、同様に、ICUから退院された患者さんは「ICUサバイバー」という呼び方をします。
病院というと、外来を受診したり、たとえ入院が必要となったりしても、いったん治療を受けて良くなれば、元通り元気になると考える方が多いのではないかと思います。しかし、重症疾患とその治療を経験したICUサバイバーは、必ずしも入院前の状態に戻れるとはかぎりません。長期に渡って筋力が低下したままであったり、認知機能が低下したり(例:車を停めた場所を覚えていない、簡単な計算ができない、IQが低下する)、うつやPTSDといった精神的な問題を抱えたりという長期的な合併症を起こすことがあるのがわかってきたのです。そのため、退院したあとも、仕事に戻れなかったり、人間関係を築けなかったり、自分が自分でなくなったように感じたりすることがあります。このような、ICUを退室したあとの長期的合併症は、集中治療後症候群(Post-Intensive Care Syndrome:PICS)と呼ばれ(「ピックス」と読みます)、ICUサバイバーの生活の質に大いに影響します。PICSは決して高齢者のみの現象ではなく、どのような年齢のどのようなICUサバイバーにも起こりえます。
新型コロナで重症患者が増える中、ICUサバイバーの抱える問題に警鐘を鳴らし、対応策を提示するのが本著です。著者のE.ウェズリー・イリー先生は、集中治療の世界では知らない人がいないほど世界的に有名な集中治療医で、この分野の研究の第一人者です。PICSによってどれほど人生が変わってしまうのか、ならないようにするため患者と家族、医療者に何ができるのか、退院後にどのように対応すれば良いのかを豊富な経験と研究結果から示して下さっています。対応策の一つとして、ICU入院中の鎮静を減らし(または、なくして)覚醒を保ち、早期から離床することが挙げられています。離床というのは「床(とこ)を離れる」という文字通り、ベッドから起き上がって、立ち上がったり、歩行したりして過ごすことを指します。ICUに入院するような重症患者でも、このような治療が可能であり、かつ重要であると本書では実例を挙げて説明しています。
医療者は、これまで患者さんのためによかれと思って、鎮静薬を使ったり、病状が改善するまでのあいだベッド上安静にしたりしてきました。「患者さんが不快に感じるのではないか」、「チューブなどを抜いて自らを傷つけるのではないか」と心配だったのです。しかし、現在では、重症になった原因そのものに加えて、治療のために使用する人工呼吸器や、人工呼吸器を安全に使用するための(あるいは、そう思って使う)鎮静薬、長期の安静などの影響によって、せん妄が増えたり、長期的な認知機能障害につながったりすることがわかってきています。これまで、私たち医療者は「ベッドの右側」に立った医療者の目線(チャプター6)だけから患者さんを診てきました。短期的にだけではなく、長期的にも患者さんとご家族にとって真に意味のある結果が得られるよう、医療の考え方を見直す時期に来ています。「善意」だけでなく「善行」の時なのです。
医療を受ける側からすると、これまでは自分や家族が入院しても、医療者に全てお任せにすることが多かったかもしれません。新型コロナによる面会制限がある状況では、特にそうだったのではないでしょうか。医療者の立場からすると、信頼していただけるのは非常に光栄なのですが、自分や家族への医療を医療者に丸投げしてしまうのはおすすめしません。本書で繰り返し述べられているように、患者本人と家族の参加は不可欠です。ICUでの治療を要するような重症の場合、患者さんを代弁したり精神的にサポートしたりなど、家族にしかできないことも多々あります。退院後の長期の脳機能障害にも相関する「せん妄」という状態は(チャプター5)、患者の様子が「いつもと何か違う」のに家族が気付いて見つかることもあります。もちろん、医療者のすることに何でもかんでも難癖をつけろという意味ではありません。むしろその逆に、患者さんがなるべく早く元の生活に戻るという共通の目標に向かって、患者本人と家族、医療者がみな協力できる関係を築くのが重要です。
本書に登場する米国ユタ州ソルトレイクシティーのLDS病院(チャプター9)は、現在私が集中治療医として勤務する病院です。テリー・クレマー医師はかつての上司かつわたしの前任者であり、ナース・プラクティショナーのポーリー・ベイリーとは今でもICUで共に勤務しています。そのような繋がりがあり、また本書で扱う患者中心の「思いやり」の医療を私たちのチームも共有しているため、翻訳の機会を戴けたことは非常に嬉しく感じています。そして、日本語版を最善の形で出版できるようにと、翻訳に際しての質問に逐一答えて下さったE.ウェズリー・イリー先生に感謝します。
社会が高齢化しており、また新型コロナによる重症患者が数多く出ているため、今後PICSへの対応が一段と重要になると予想されます。本書の内容は、一般の読者はもちろん、ICUでの診療を改善したい医療者にとっても役に立つものです。ICUサバイバーを理解し、認め、手助けするのに役立てていただければ幸いです。
田中竜馬
目次
はじめに
略語一覧
プロローグ
Chapter1
壊れた命 新しい日常を受け入れる
Chapter2
集中治療初期の歴史 ICUという高速道路に向かうデコボコな砂利道
Chapter3
集中治療の文化 深い鎮静と安静の時代
Chapter4
移植医療の世界 正しい道を模索する
Chapter5
せん妄という大惨事 患者と家族にとっての目に見えない災難
Chapter6
ベッドの反対側から見た風景 病気を見直す
Chapter7
進むべき道を決める 臨床と研究の融合
Chapter8
脳を解き放つ ICUで意識を見つける
Chapter9
目覚めの変化 患者が再浮上する
Chapter10
情報を広める 新しいアイデアの実践
Chapter11
患者の中に人を見出す 人間らしさによる希望
Chapter12
ICUでの終末期ケア 患者と家族の望みが実現する
エピローグ
謝辞
許諾一覧
書籍案内
索引
