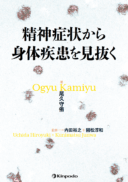精神科医もできる! 拒食症身体治療マニュアル
第2版

★2025年6月中旬 発売予定!★
精神科単科病院でも安全に神経性やせ症(拒食症)の治療が可能に。主治医不在でも同じ水準を維持できるよう設計された身体管理マニュアル
内容紹介
神経性やせ症(拒食症)は、精神疾患の中で最も死亡率が高く、低栄養や合併症が主な死因です。加えて、栄養療法に伴うリフィーディング症候群(再栄養症候群)は致死的となるため、精神科医が治療を敬遠する傾向があります。そのため従来の治療体制は総合病院に限られてきましたが、精神科病床の減少により限界が見え始めています。
こうした課題を受け、浜松医科大学精神科神経科では、精神科単科病院でも活用可能な身体管理マニュアルを開発しました。栄養療法開始日を基に検査内容や投与量、薬剤選定まで明確に規定しており、当直帯でも質の高い医療を提供することが可能となりました。導入後はリフィーディング症候群の発生ゼロ、検査の漏れや苦情の減少、入院期間の短縮と大きな成果が得られました。
初版出版当時は、リフィーディング症候群の予防策として摂取カロリーが極端に低い食事で栄養療法を開始することが推奨されていました。しかし、近年では低栄養状態が遷延することの弊害も考慮されるようになり,より高い摂取カロリーでの栄養療法が提唱されつつあります。そのため、今回の改訂では患者のBody mass index に応じて投与カロリーを増加させ、一部の薬品をより病態に適したものに切り替えました。また、治療を簡略化し、より簡便に運用できるマニュアルを目指しました。
本書がより多くの現場で活用いただけることを願っております。
序文
監修のことば
本マニュアルの初版が出版された翌年の2015年、厚生労働省の主導で『摂食障害治療支援センター設置運営事業』が始まりました。本事業は全国に摂食障害の治療体制を整えるべく、各都道府県に拠点病院を作る目的で発足しました。当初は拠点病院が4つしか設置されず、うち精神科の拠点病院は私ども浜松医大のみでした。事業の中で摂食障害の入院治療体制の整備を全国に普及する研修会を開催していただき、本マニュアルを含めた浜松医大の入院治療のノウハウを広めてきました。その後、全国の多くの精神科施設に本マニュアルを導入していただき、「治療が非常に楽になった」「病棟で多くの患者を診療できるようになった」との声をいただきました。また、本マニュアルを導入していただいた大学病院精神科や精神科単科病院が、摂食障害の拠点病院となっています。このように、摂食障害治療の普及に本マニュアルを少なからずお役立ていただいております。
低体重の患者の治療において再栄養症候群(refeeding syndrome:RS)の予防や治療は重要な問題ですが、一方で昨今、underfeedingすなわちエネルギー摂取量が低すぎるデメリットが叫ばれるようになり、世界的にも治療開始時から高いエネルギー摂取量を投与する試みが報告されてきました。治療開始時から2000kcalを超えるような高いカロリー投与を推奨する欧米の報告もありますが、これらの報告では治療開始時のBMIが15を超えるような患者を対象にしています。本マニュアルの初版が発行された当初、浜松医大への拒食症入院患者の平均BMIは12程度であり、非常に低体重の患者が中心でした。したがって、わが国で入院治療対象となるような極低体重の患者に欧米の基準を当てはめて高カロリーを投与するは極めて危険です。これまで拒食症の患者に身体治療マニュアルを使用して治療することで、RSの発現率は7.6%と極めて低くいことがわかりました。さらに詳細なデータ解析から、RSの発現し得る治療開始時のBMIのカットオフ値は11.5と算出されました。すなわち、治療開始時のBMIが11.5を超えていれば、身体治療マニュアルを使用することでRSの発現が回避し得ることが期待できます。これらデータをもとに、我々の施設ではBMI13を超える患者に対しては、underfeedingを回避するべく、従来のマニュアルに比べて1400kcalという少し高いカロリー投与で治療を開始する修正を行い、今のところ安全に治療を行うことができています。改訂版ではこのような修正が反映されています。
今後、新たに摂食障害治療を始められる施設、あるいは、これまで治療に苦慮してきた施設におかれましては、是非、本書をご活用いただき、拒食症の安全かつ効率的な治療の一助にしていただけることを願っております。
浜松医科大学医学部附属病院精神科神経科講師
竹林淳和
序文
2014年に拙著「精神科医もできる!拒食症身体治療マニュアル」を上梓して以来、全国から好意的な意見を多数お寄せていただき、大変な励みになっている。他方、神経性やせ症の治療に関して治療者が栄養療法、つまり体重を増加させることに固執することを危惧する意見も聞かれた。もちろん精神疾患の生物心理社会モデルに鑑みて心理社会的介入が重要であることは言うまでもない。欧米で神経性やせ症に対する治療効果が実証された心理療法としてモーズレイ式神経性やせ症治療(MANTRA)や強化された認知行動療法(CBT-E)が知られているが、これらを導入するためには全身状態が安定していなければならない。包括的な介入を行うためには適切な身体治療の手法もやはり欠かせないだろう。筆者は神経性やせ症の身体治療を主体的に行うようになってから全身管理にかかる不安は軽減し、むしろより多角的な視点から治療に取り組めるようになったという実感がある。
本書出版当時、リフィーディング症候群の予防策として摂取カロリーが非常に低い食事で栄養療法を開始することが推奨されていた。しかし、近年では低栄養状態が遷延することの弊害も考慮され、より高い摂取カロリーでの栄養療法が提唱されつつある。そのため、改訂版となる本書では患者のBody mass indexに応じて投与カロリーを増加させた。また、一部の薬品をより病態に適したものに切り替えた。さらに、治療を簡略化することでより簡便に運用できるマニュアルを目指した。
本書がより多くの治療者の手元に届き、より多くの患者さんの治療に役立てていただければ幸いである。
エールこころのクリニック
院長 栗田大輔
目次
監修のことば
改訂にあたって
はじめに
本書の特徴
目次
1章 治療を始める前に
リフィーディング症候群
病態生理
治療経過の概要
適応
2章 治療マニュアル
注意事項
入院当日(Day0)
第1期(Day1~4)
第2期(Day5~10)
第3期(Day11~28)
第4期(Day29~)
3章 緊急時の対応
バイタルサインの異常
低血糖
高血糖
4章 約束処方とセットオーダー
約束処方
セットオーダー